【前編】 地域に開かれたランドスケープ、カフェ、広場、通り抜けできる道。まちの一部としての施設と外構を設計。
設計事例:アクティブシニア向けレジデンス「パークウェルステイト湘南藤沢SST」
■エンドユーザー目線を保つ一気通貫のアプローチ
—— まず、UDS株式会社とCOMPATH(コンパス)事業部の特徴について教えてください。
高宮:UDSの最大の特徴は、企画から設計、施工、運営まで一気通貫で行うことです。クライアントの期待にこたえることはもちろんですが、コーポラティブハウス事業から始まった会社ということもあり、常にエンドユーザー目線を重視し、「土地やまちにとって最適な場は何か」を考えることから始めます。
小泉:COMPATHは、UDSの中でも企画設計を中心とした部門で、建築からインテリア、ランドスケープの専門性を持つチームで構成されています。前職でランドスケープとまちづくりに関わってきた私がUDSに入社した理由も、設計だけでなく事業の企画段階から「その場所に何が必要か」を考える姿勢に魅力を感じたからです。
高宮:私は建築出身ですが、家具から建築、エクステリアまで一体として考える必要があると思っています。建物だけでなく、内部・外部の環境も含めてトータルで価値を創出することが重要です。
—— ランドスケープデザインにおける、UDSならではのアプローチはありますか?
小泉:まちの価値を最大化する「まちづくり」の視点を常に持っていることですね。行政と連携したPPP事業なども手がけていますが、単なるデザイン提案に留まらず、その場所に応じた事業性や必要性を踏まえた説得力のある説明ができます。
高宮:ホテルをはじめとしてUDSが運営やメンテナンスまでの実績を持つため、クライアントへの提案にも説得力が生まれます。デザインだけでなく、その後どう運営していくかまで見据えて提案できるのが強みです。
■地域のランドスケープの豊かさを活かしたデザイン
—— 具体的なプロジェクトとして、「パークウェルステイト湘南藤沢SST」について伺います。背景や特徴を教えてください。
高宮:事業主は三井不動産レジデンシャル株式会社で、Fujisawa SST(Fujisawaサスティナブル・スマートタウン)の区画に位置するプロジェクトです。私たちは共用部インテリアに加えて、共用棟外装、そして全体ランドスケープのデザインの監修を担当しました。アクティブシニア向けの住居機能に加え、地域に開かれたランドスケープ、カフェ、広場、通り抜けできる道など、まちの一部としての施設と外構が求められていました。
湘南エリアの魅力は、ランドスケープの豊かさだと思います。ですから、それを活かしたランドスケープデザインを軸に構築することを提案しました。建物の「顔」は一般的に建築物の外装にもたせるものですが、ここでは緑豊かなランドスケープやエクステリアを一体として定義。クライアントには基本計画の段階で「計画全体の基壇部はグリーン」「林のような豊かな樹木で挟まれたアプローチ」という考え方に同意していただけました。エクステリアは生活の延長であり、必要不可欠なアートの一部という提案です。ランドスケープデザインの重要性が共通認識となったため、コスト削減の対象になりがちなランドスケープの予算と考え方を竣工まで保つことができました。

©Nacasa & Partners
小泉:建物を直接的に見せるのではなく、木立の間から垣間見えるようにすることで、ヒューマンスケールで居心地の良い空間を演出するという思想をクライアントと共有できたのは大きかったです。
高宮:外部のアプローチの脇には石積みの立ち上がりを設けていますが、エントランスを入ったロビーラウンジの壁面にも連続して使用しています。外のデザインボキャブラリーを室内でも用いることで、内外の一体感を創出しました。またインテリアにもグリーンを設えて、外部からの延長となるように見せています。

©Nacasa & Partners
小泉:ロビーラウンジではインテリアグリーンを空間の重要な要素として活用し、視線の先に緑が見えるアイストップの効果を生み出しています。
高宮:高さ3mほどの植栽を植えた鉢植えを設置したほか、外部と同様に土を敷き込んで本物の植物を植え込む手法を基本としました。ここでは植栽帯への立ち入りをゆるやかに防止するため、アート作品を設置した台座を「結界」のように用いることで、機能性とデザイン性を両立させました。ただし、植物が枯れるリスクを前提として、持続的に共存するための仕組みを構築することが重要です。

©Nacasa & Partners
小泉:ここではレンタルグリーンも活用し、定期的に植物を交換し養生する体制を整えました。造園業者やインテリアグリーンの専門家と連携し、メンテナンスは週に1回なのか月に2回なのか、など長期的なメンテナンス計画を立てることで、常に良い環境を維持できる体制をクライアントに提案しています。
—— 樹木や植栽の選定で注意されたことはありますか?
高宮:種類に固執せず、クライアントとはイメージを共有することに注意しました。樹木選定の段階で枝ぶりなどが良いものが入手できる場合、当初の想定とは異なる樹種でも融通をきかせることができるためです。一方で、共用棟の通り側の象徴的なヤシの木は当初は中央に配する計画だったのですが迫力ある木が手に入ったことから、カフェのエントランス脇にずらして配置し直すことで、施設のサインとしての役割を持たせました。現場の状況に応じて、配置も柔軟に変更しています。
小泉:敷地内のエリアごとに、少しずつ異なる世界観をデザインしています。カフェから見える緑はヤシなどを使って湘南らしい雰囲気を演出し、中庭は雑木林のような樹種を選んで林の中を散策しているような居心地の良さを目指しました。このような世界観に合わせて、歩く場所の仕上げ材の色合いや素材も決定しています。
■アクティブシニアの「背中を押す」ランドスケープデザイン
—— 施設の入居者層に合わせた工夫はありますか?
高宮:この施設を利用される方は、歳を重ねても元気で活発な「アクティブシニア」です。快適で整った環境であることが基本となりますが、画一的な空間の繰り返しでは季節の移ろいなどの環境の変化に気づきにくくなるので、自然に外へ出たくなるような「背中をそっと押す」きっかけを作るデザインを求められました。日の光や風、雨上がりの石の照り、草木や花の香りなど、五感で自然を感じられる発見が、居住される方を中から外へと誘い出す仕掛けとなります。また、完全な安定を優先して活動を制限するのではなく、安心安全な上で心身に良い刺激を与える環境を提供することを重視しています。
例えば、上階のライブラリースペースのテーブルにはプランターを仕込み、そのテーブルとグリーンが外のテラスにも続いて景色が一体化して感じられるような演出を行いました。ダイニングの天井はシンプルな塗装仕上げとし、植栽下部からのライトアップにより葉の影が模様となって天井に映し出され、植栽単体以上の豊かな表情を生み出しています。

©Nacasa & Partners

©Nacasa & Partners
外部通路では人工物と自然物をフラットに捉えて、歩行部分を植栽部分と明確に分けずに、緑が少しはみ出してくるように計画しました。また、木立に馴染むようなガラスや金属等のアートオブジェを配して、ランドスケープとの一体感の中で、入居者たちが身体の延長でアートに触れられる計画としました。季節が移り木々が変化するとともに、自然と一体となったアートの感じ方も変わることを期待しています。

©Nacasa & Partners
小泉:床の仕上げでも、芝の中に飛び石を設けたり、洗い出し仕上げとするなど、共通して手触り感があって屋外空間を感じられるようにしました。例えば、広場脇で軒下に訪れた人が滞留するスペースでもそのような仕上げとし、高齢者と地域の子供たちが自然と寄り添える場となるよう設計しています。また、広場内には菜園と水場を設けており、高齢者が野菜を育てる様子を子供が見るなど、施設に入ることで離れがちな世代間の交流を促すきっかけ作りを意図しました。

©Nacasa & Partners
高宮:石のベンチでは座り心地を確かめながら、座面部分を磨くなどの技術的な工夫を重ねました。家具のクッションについても、柔らかすぎるとシニアが立ち上がれなくなるリスクを考慮し、モックアップを作成して適切な硬さを追求しました。
—— 仕上げなどでは、天然素材を多用されていますね。
高宮:はい。内外装には本物の岩や石を多く使用しています。「〇〇調」「〇〇風」といった既成品はメンテナンスの面ではよいのですが、自然の力強さを感じさせたかったからです。本物の石など天然素材の使用は複数回にわたる検討・選定がともないましたが、クライアントとともに意識を共有しながら、粘り強く実現しました。
同時に、ウッドデッキなどのエクステリア製品については周囲の自然から浮いて見えないよう、素材感や色合いに注意して選びました。近年の製品は質感や彫りの具合が進化していて、植物の陰影が複雑に出るようになり、自然の要素との相性が向上していると感じます。

©Nacasa & Partners
——フェンスや柵については、いかがでしたか。
高宮:このプロジェクトでは、まちへの貢献という要素が重視されていたため、閉鎖的な境界ではなく開かれたデザインを心がけました。敷地の境界についても重厚なフェンスで囲う手法ではなく、植栽と一体化したメッシュフェンスを多用しています。メッシュフェンスは風や光を通し景観と馴染みつつ、最小限の線の細さで境界を明確にできるスマートな選択肢だと捉えています。
小泉:黒色等のメッシュフェンスを植栽や樹木と組み合わせることで、グリーンとフェンスが一体化し、存在感を和らげることができます。もちろん、安全や安心感を確保するためにコンクリートや目隠し壁を作ることはありますが、あくまで主役ではないので、緑と重ね合わせていくことで違和感のないものにすることもできます。
——プロジェクトの成果はいかがでしたか?
高宮:私たちが提案したのは、まちの人に対して開き、土地の魅力を活かすランドスケープやエクステリアでした。それが都心の施設とは異なる価値観として受け入れられ、多くの方々に利用していただける「まちの緑場」と成熟してくれれば嬉しいです。

©Nacasa & Partners

高宮大輔(たかみや・だいすけ)
UDS株式会社
取締役 兼 COMPATH 上席執行役員
千葉大学大学院卒業後、2001年都市デザインシステム(現UDS)入社。株式会社コプラスを経て2013年にUDSに復帰し、商業・宿泊施設から住宅まで幅広いジャンルの建築設計・空間デザイン・家具デザインに携わる。
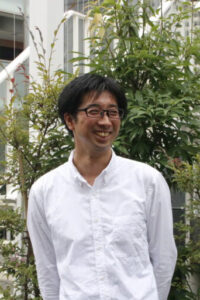
小泉智史(こいずみ・さとし)
UDS株式会社
COMPATH 執行役員
大学院修了後、ランドスケープ設計事務所でランドスケープの設計に従事したのち、事業会社でまちづくりに携わり、2016年にUDSに入社。ランドスケープ担当者として、国内外を問わず屋外空間の提案を幅広く担当。
著者プロフィール

最新の投稿
 パブリックエクステリア2026.02.24【後編】一般的なゲートで囲われた住宅開発とは異なり、オープンな交流ができる「居場所」を目指して、「ウェルネス」「アート」「ロマンス」「コミュニティ」「ネイチャー」という5つのテーマを設計、あえてそれぞれに異なる機能を持たせることで、敷地全体に多様な目的地となる場を生み出した。
パブリックエクステリア2026.02.24【後編】一般的なゲートで囲われた住宅開発とは異なり、オープンな交流ができる「居場所」を目指して、「ウェルネス」「アート」「ロマンス」「コミュニティ」「ネイチャー」という5つのテーマを設計、あえてそれぞれに異なる機能を持たせることで、敷地全体に多様な目的地となる場を生み出した。
住宅、オフィス、美術館、商業施設、ホテルなどが含まれる大規模な複合開発。
設計事例:中国杭州市「Light of Future」プロジェクト パブリックエクステリア2026.01.27【前編】「伝統・自然」と「ビジネス・革新・未来」という明確な二面性を持つ敷地の文脈を深く読み解き、それをデザインに反映。
パブリックエクステリア2026.01.27【前編】「伝統・自然」と「ビジネス・革新・未来」という明確な二面性を持つ敷地の文脈を深く読み解き、それをデザインに反映。
都心のオープンスペースにおいて、人の流れとアクティビティーを重要視し、場の多様性と魅力を高めるように13のゾーンを構築するサイトフレームワークを設定。舗装、植栽、水景、照明、ファニチャーなどのデザインを通して、空間特性を演出した。
設計事例:東京 大手町「Otemachi One Garden」プロジェクト パブリックエクステリア2025.12.23【後編】 駅ビル商業施設の既存建物のリニューアル。施設全体を「公園」と捉え直し、豊かなランドスケープによる動線の再整理で施設全体の活気を創出。 設計事例:韓国ソウルの「HDC I’PARKmall」リニューアルプロジェクト
パブリックエクステリア2025.12.23【後編】 駅ビル商業施設の既存建物のリニューアル。施設全体を「公園」と捉え直し、豊かなランドスケープによる動線の再整理で施設全体の活気を創出。 設計事例:韓国ソウルの「HDC I’PARKmall」リニューアルプロジェクト  パブリックエクステリア2025.11.25【前編】 地域に開かれたランドスケープ、カフェ、広場、通り抜けできる道。まちの一部としての施設と外構を設計。
パブリックエクステリア2025.11.25【前編】 地域に開かれたランドスケープ、カフェ、広場、通り抜けできる道。まちの一部としての施設と外構を設計。
設計事例:アクティブシニア向けレジデンス「パークウェルステイト湘南藤沢SST」